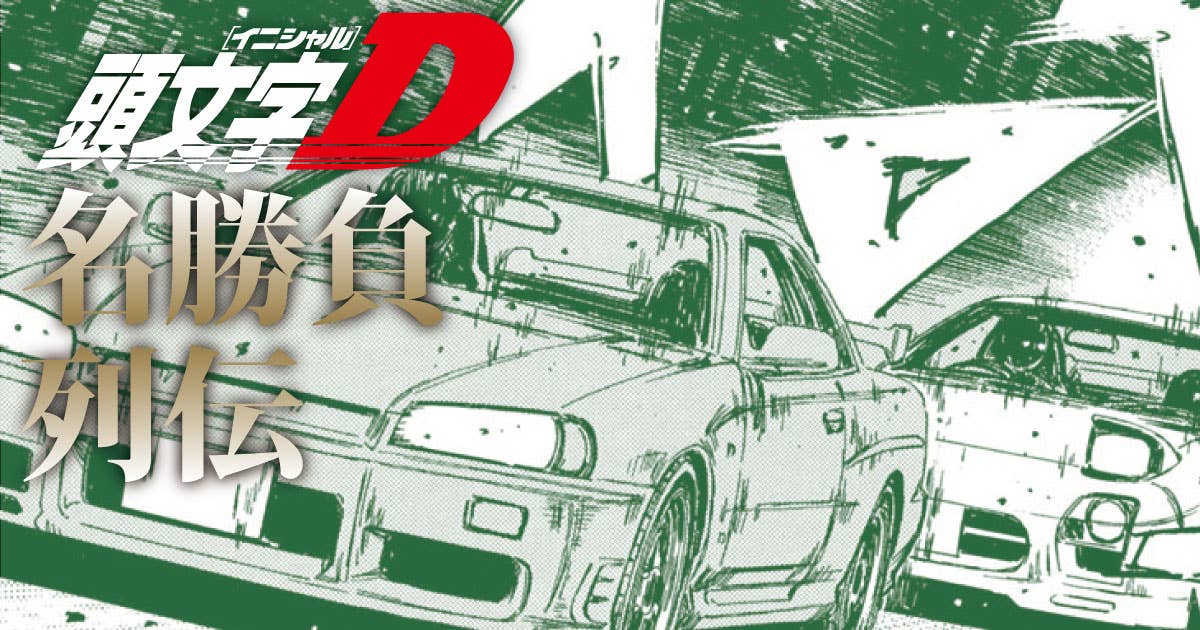伝説のクルママンガ『頭文字D』の名勝負を選出した「頭文字D名勝負列伝」が、読者のアンコールに答えて復活! 記念すべき20回目となる今回は、人気の名車、RX-7とスカイラインとのバトルを紹介する。これはプロジェクトDにとって記念すべき最初の遠征試合でもあった。
文/安藤修也
マンガ/しげの秀一
【登場車種】
■先行:日産・スカイライン25GTターボ(R34型)
→ドライバーは「セブンスターリーフ」ヒルクライム担当の川井敦郎。短髪に太眉、たらこ唇と、なんだかゴツくて気の強そうな顔立ちだが、チームメイトへの発言や振る舞いなどからは優しさがにじみ出ている。日頃はサーキットを走り込んでいてグリップ走行が得意な理論派ドライバーだ。愛車はR34型スカイラインのGTターボで、GT-Rではないがチューニングで400馬力まで性能を高めている。
■後追い:マツダ・RX-7(FD3S型)
→ドライバーは高橋啓介。兄の高橋涼介とともに赤城レッドサンズの2枚看板として、群馬にその名を轟かせていたが、涼介が計画した県外遠征計画「プロジェクトD」にエースドライバーの1人として参戦する。
【バトルまでのあらすじ】
藤原拓海が「頂点に立つドライバーになりたいんだ」とこっそり宣言し、秋名山での渾身のタイムレコードを記録し、さらに愛する人との別れを経験したところで、『頭文字D』の第一部は終了した。
第二部は、高橋涼介による県外遠征チーム「プロジェクトD」の始動とともにはじまるが、今回紹介するバトルは、その最初の遠征試合である。舞台は栃木県F町、プロジェクトDの最初の挑戦を受けて立ったチーム、その名は「チーム・セブンスターリーフ」だ。
同チームのリーダーである末次トオルの生き方には、日々の金欠や彼女との未来、走り屋としてのけじめの付け方など、走り屋の若者のリアルというか、等身大の姿が描かれている。その一方で、トオルや敦郎の目線から見たプロジェクトDの面々は、自分たちと比べてどこか異質で、次元の異なる天才集団に映っていた───。

【バトル考察】
まず最初にダウンヒル対決が行われた。ロードスターのトオルは奮戦したものの、ハチロクを操る拓海とのレベル違いの走りに驚愕。最後は意地を張りすぎてしまい、側溝にタイヤを落としてクラッシュ、そのまま横転して敗北を喫した(幸いにもトオルにほぼ怪我はなかった)。
続いてヒルクライム。敦郎の番だが、拓海の走り=プロジェクトDの実力を目の当たりにして、スタート前から焦りを感じている。しかし、クラッシュするまで攻めきったトオルの頑張りに気持ちを奮い立たせ、スタートラインに立つことになる。
1本目のスタートはの立ち位置は、敦郎のスカイラインが前。スカイラインGTターボとRX-7という2台のハイパワーターボFR車が、迫力の排気音とともに猛然とダッシュする。プロジェクトDとの格の違いを実際に味わったトオルは、「勝ち目はないかもしれねーけど、せめて一本目は逃げ切れよ」と心の中で敦郎にエールを送る。

馬力で勝るスカイラインだが、FDは引き離されない。敦郎もすぐに「この黄色は、今までの相手とは格がちがう」と再確認したものの、「オレはオレの走りで行く!!」と、ドリフトなどハデなアクションなしの、サーキットでラップタイムを出す時のグリップ走行を実践する。
さらに、「ヒルクライムは馬力(パワー)だ!!」と言い切り、「この34の大がらなボディは、意識してブロックをしなくてもスペースをつぶしてくれている」と、ストレートでもコーナーでも有利であることを主張した。
ダウンヒルでハチロクが見せた側溝の上をショートカットする走法(ミゾ落とし)を阻止しようと、スカイラインはインを防いでいたが、RX-7に乗る啓介には拓海と同じ攻め方をするつもりは毛頭なかった(啓介の性格を知っていれば当然のことだが)。

コーナーをコンパクトにまとめてアクセル全開の時間を少しでも長くとることに重点をおいた走りを敢行するスカイラインに対し、後方にピタリとつけたRX-7のハンドルを握る啓介は、「甘いぜ、あんたの弱点見切った!!」と何かを悟る。
そして実際に、RX-7は終盤のコーナー立ち上がりでスカイラインに並び、そのまま抜き去った。「拮抗していたかに見えた2台のバトルは、この一瞬、あっけなく幕を閉じる」というナレーションの言う通り、あまりにも簡単な幕切れに、抜かれた敦郎はもとより、セブンスターリーフのメンバー、そして見ていた読者も呆気にとられるのだった。

バトル後、納得がいっていない敦郎は、高橋啓介のもとへ駆け寄り、尋ねた。「直線(ストレート)の加速は、こっちのクルマの方が上だと感じていたのはオレの錯覚なのか?」と。油断させるため、啓介がそれまで全開にするのを抑えていたと思ったのだ。
しかし実際はそうではなかった。啓介の答えは「立ち上がり重視のコーナリング」。それは走りの基本中の基本であり、敦郎も理解しているつもりだった。啓介の説明がいまいち下手だったというのはあるが(笑)、つまり、RX-7の走りが常識をも超えた凄まじく高いレベルにあったということでもある。
また余談だが、この時、「信じたくねーかもしれねーけど、現実をうけとめないと進歩はないぜ‥‥」となかなかキビしい発言をするところも啓介らしい(笑)。
敦郎は「なんかもう、どうしようもなく、すげえや‥‥」と諦めの境地に至り、さらにトオルは走り屋をやめることになる。多くの走り屋たちは、いつか気づいてこの道の頂点を諦める。それがプロジェクトDに出会ったから早まっただけである。
※この記事はベストカーWebの記事を再編集したものです。
→バックナンバーはこちら!
『頭文字D』はヤンマガWebで配信中! ▼▼今すぐ読む!▼▼

▼▼しげの秀一最新作『MFゴースト』はこちらから!▼▼